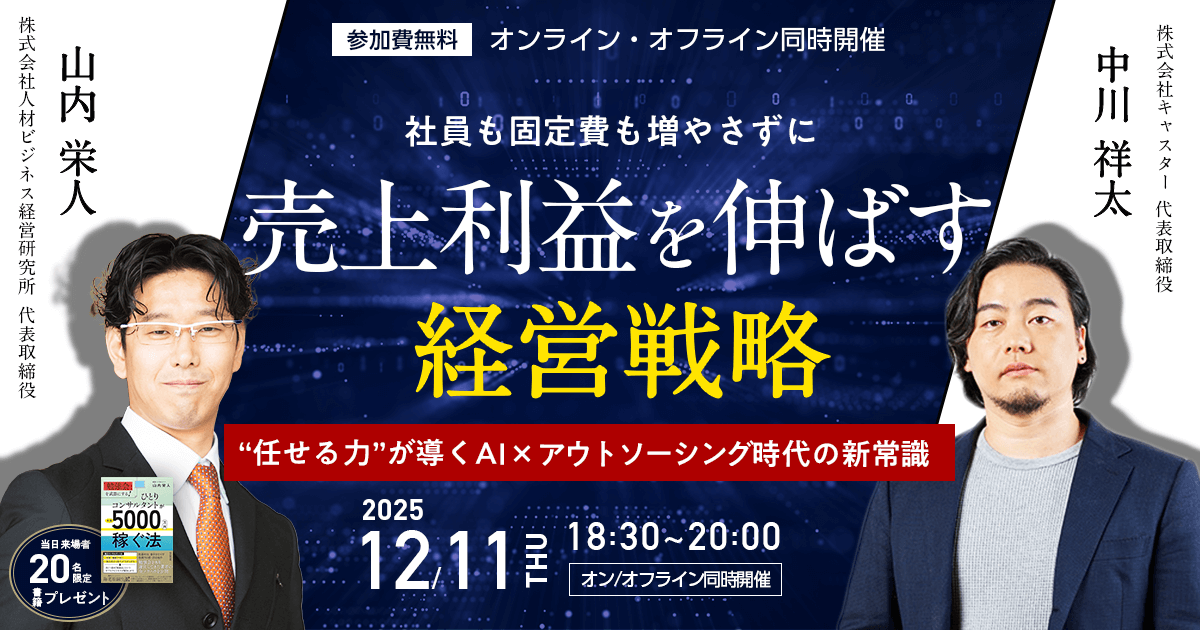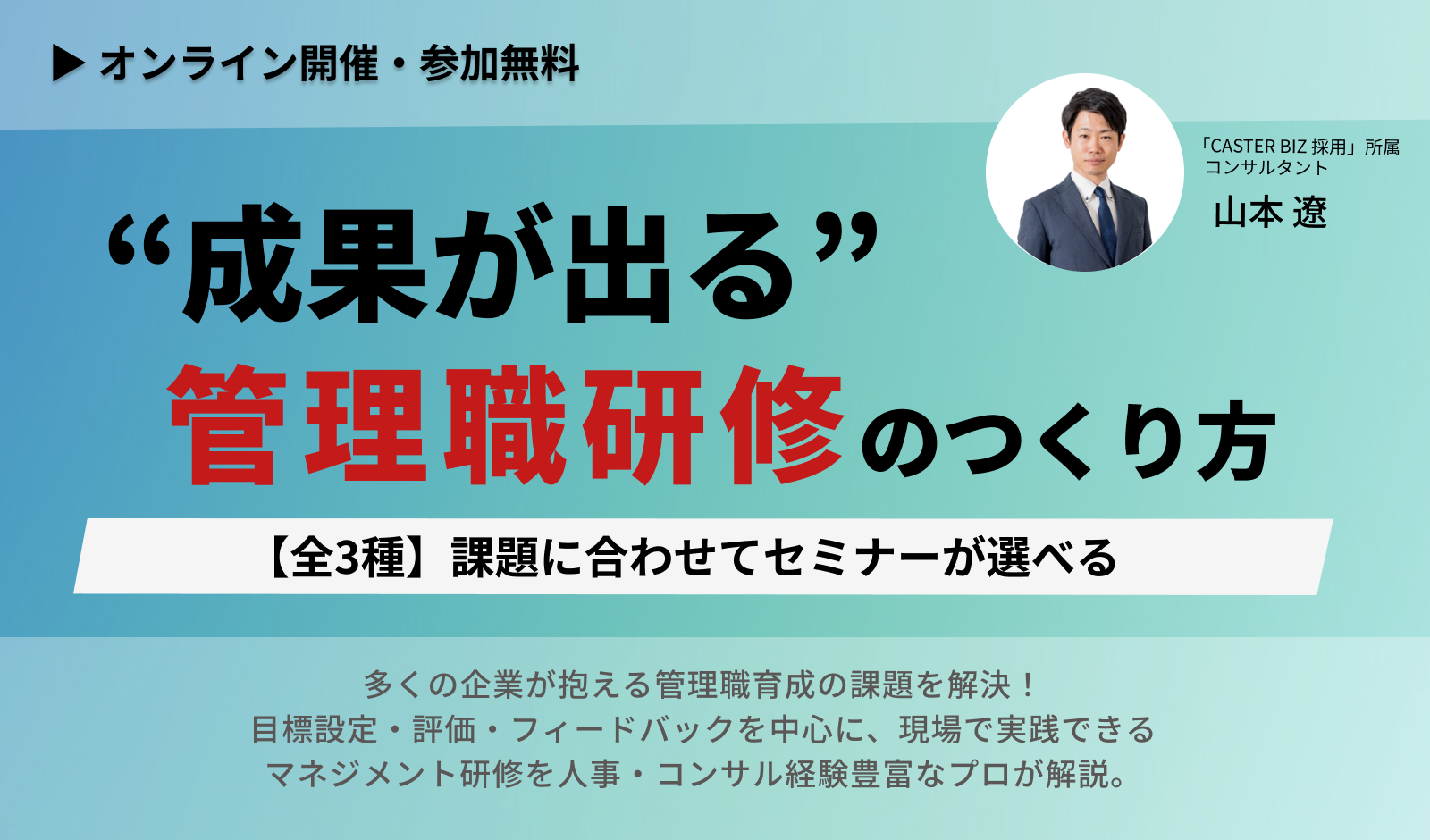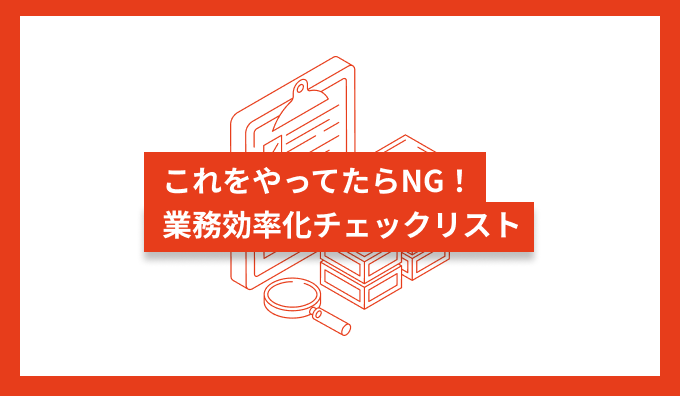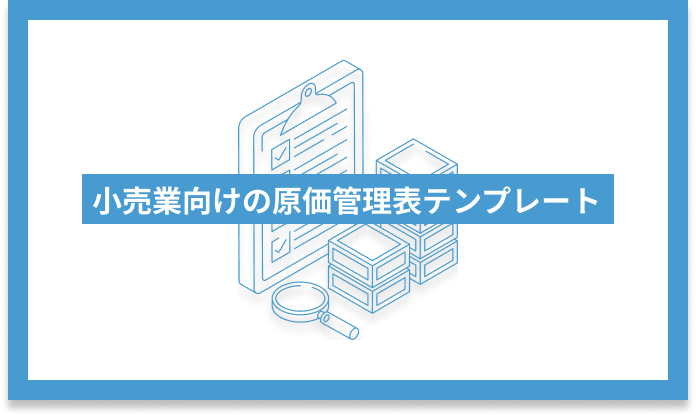ブラック企業とは違い、居心地は良いけれど働きがいがない「ゆるブラック企業」。働き方改革によって、意図せず“ゆるブラック化”している可能性もあります。ゆるブラック企業の特徴と、AI時代にゆるブラックな組織に潜むリスクについて考えます。
「ゆるブラック企業」って何?
「ゆるブラック企業」というものをご存じでしょうか?
残業はなく、厳しすぎるノルマや精神的なプレッシャーもほとんどなく、働き手からすると“ゆるい”環境ではあるが、一方で働きがいは感じられず、昇進や昇給も望みが薄く、スキルアップもキャリアアップも期待できないーーそんな企業が「ゆるブラック企業」と呼ばれているそうです。
従来、いわゆる「ブラック企業」と言われてきた企業は、ハラスメントや長時間労働が当たり前の環境でした。ゆるブラック企業はそれとは異なり、働く環境が整備されているのが特徴のよう。
働くうえで心身の危機にさらされたり、ハラスメントの被害を受けることはなくても、職場としての魅力が低いという点で“ブラック”と言われているのです。
終身雇用の制度が揺らぎ、人生100年時代の今、幅広いスキルやハイレベルな技術を身につけてキャリアを切り拓きたいと考える人は増えています。ゆるい職場で働き続けることに、不安を感じる人は少なくありません。
身近に蔓延している…ゆるブラック企業の実態
「ゆるブラック企業」は、実はそれほど珍しい言葉ではありません。調査(※1)によれば「ゆるブラック企業」という言葉を知っている人は43%。年代が上がるほど知名度が高く、40代以上では47%と半数弱が認知しているようです。
※1 エン・ジャパン「社会人5700人に聞いた「ブラック企業・ゆるブラック企業」調査」
また、20代と30代を対象にした調査(※2)では、41.9%が「現在の勤務先は、『ゆるブラック』だと思う」と回答。そのうち41.1%が、今後1年以内に転職しようと考えていたり、実際に転職活動を行っていたりすることがわかりました。
※2 アデコ「「ゆるブラック」に関する調査」
ゆるブラック企業が広まった背景には、2019年ごろから始まった働き方改革や、2022年4月から中小企業にも適用された「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」が考えられます。
長時間労働やパワハラに対して罰則付きの規定ができたことから、各企業が職場環境の改善に取り組んできました。その結果、ブラック企業と言われる状況が減ったのは成果といえます。一方で、それらを意識しすぎたあまり、業務のために本来必要だった上司からの指導やメンバー間の切磋琢磨・競争ができず、一部でゆるブラックな環境ができあがったのかもしれません。
また、働き手から、スキルアップのニーズが高まっていることも背景の1つです。今や転職や副業が当たり前になり、スキルを身につけられたり、人材としての市場価値を上げられたりする職場が「よい職場」とされる傾向にあります。
その結果、ゆるく働けることだけが魅力の職場は「ゆるブラック」と呼ばれ、上昇志向の強い人やキャリア形成に積極的な人からは忌避されるようになったと考えられます。
ゆるブラック企業の特徴3点
ゆるブラック企業には、具体的にどんな特徴があるのでしょうか。
昇給・昇格がしづらく、閉塞感が強い
ゆるブラック企業では、仕事で成果を出したり新しい挑戦をしたりすることが評価されにくく、昇給や昇格しづらいのが特徴です。
高度なノウハウやスキルは求められず、単純作業や定型業務が多いため、給与ベースが低く抑えられがちです。
スキルアップができない
基本的に新しい挑戦をする必要がないため、メンバー同士で議論を交わしたり、新しい挑戦に向けて努力したりすることは求められません。そのため、長期間働いてもそれほどスキルが身に付かず、人材としての市場価値が上がりにくいのが特徴です。
結果的に、同じ職種でも年次とスキルの釣り合いが取れず、転職活動時にも不利になることを働き手が懸念します。
「ぬるま湯」的な居心地のよさがある
ゆるブラック企業は、トラブルやハラスメントが起きにくいのが特徴です。人間関係がギスギスすることもなく、厳しすぎる目標やノルマによるストレスもなく、「ぬるま湯」的な居心地のよさが生まれている状態とも言えます。
その状態に魅力を感じて働き続けるメンバーも多く、離職率は高くならない傾向にあるため、皮肉なことに組織としては比較的安定しやすいといえます。
意図せず、未来を危うくする組織に
これまでのゆるブラック企業は、経営層やマネジメント層から見ても、ある意味で安定した職場に映ったかもしれません。昇進・昇格を望まず、与えられた業務だけをこなす「静かな退職」が進んでも、大きなトラブルもなく、離職率も低いーー「コストを抑えつつ安定した組織運営ができている」と捉えることもできました。
しかし、急速に進化するAI時代の今、単純な作業や定型業務はAIに代替される可能性が高まっています。人件費を抑えてきたつもりの組織も、いずれ「人に頼るコストのほうが割高」となる日が来るかもしれません。
スキルの蓄積が進まない職場は、いざという時に事業変革に耐えられないリスクを抱えます。ゆるブラックな状態を維持することは、もはや「安定」ではなく、将来への「不安定」につながる可能性があるのです。
意図せず、組織がゆるブラック化してしまってはいないか。意識的に振り返り、「働きやすさ」と「成長機会」を両立させた持続的な競争力を持った組織づくりが求められているのではないでしょうか。
『Alternative Work』では、定期的にメルマガを配信中!ニュース、時事ネタから仕事のヒントが見つかる情報まで幅広くお届けします。ぜひ、ご登録ください。
登録はこちら

さくら もえMOE SAKURA
出版社の広告ディレクターとして働きながら、パラレルキャリアとしてWeb媒体の編集・記事のライティングを手掛ける。主なテーマは「働き方、キャリア、ライフスタイル、ジェンダー」。趣味はJリーグ観戦と美術館めぐり。仙台の街と人、「男はつらいよ」シリーズが大好き。ずんだもちときりたんぽをこよなく愛する。
メールマガジン

仕事のヒントが見つかる情報をお届けしています。